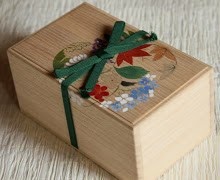そんな暑さの中、5名の参加を頂いて和裁塾開講しました。
Oさんの浴衣完成しました!!おめでとうございます。
仕上げ前でしわが目立ちますが(~_~;)ご覧下さい。
前回で袖付けまで済んでいたので、今日は振りを絎けて閂止めをして完成しました。皆さんからおめでとうの声が掛ります。嬉しい瞬間ですね。
反物が短めで、ギリギリの裁ち合わせでしたが、苦心の柄合わせ上手く行きましたね←自画自賛
そして今日からは、地色がブルーの綿縮の浴衣です。
柄合せも何とかまとまって、身頃の標付けまで進みました。
内揚げと背縫いが宿題です。頑張ってね!
Kさんは、体調を崩してしばらくお休みしていましたが、良くなってきたという事で久し振りの出席です。
両面染めの大人な浴衣をお仕立て中。今日は、脇縫いの始末です。
高級浴衣なのと、脇縫いの縫い代が多いので、開きで絎ける事にしました。
脇縫いを開きで始末するには、脇縫いを2回縫って間に忍び綴じを入れます。
その後、前裾から肩山を通って後の裾までずーっと絎けます。上等仕立てで折りぐけにしました。
中々骨の折れる仕事です。慎重に丁寧になさっていました。
浴衣が3枚目のKさん、大分要領をつかんできました(*^^)v
Tさんは、今日も部分縫いです。
女物単衣羽織の片身頃と衿付けです。
羽織の衿付けは難しいですね。なかなか苦戦しました。
その後は、袷羽織の片身頃と衿付け、袷になるとマチの止め身八つ口縫いとポイントが増えて大変です。
衿付けは、単衣と同じになります。
がんばってね(^_-)-☆
Sさんは、お久し振りの参加でした。麻長襦袢の直しです。
身丈を長くしたのですが、片方の衿先の縫いこみが短かったので、衿をすべて解く事になりました。
今回は、竪衿の衿先と絎けです。
本ぐけは前回ご説明済みだったのですが、あまりにお久し振りだったので、いつのまにかまつり絎けになっていました(@_@;)残念!
やり直して、上衿付けへ進みました。
衿の布が半端だったので新しくさらしで作りました、標を付けて衿先布を縫い付けて、身頃の衿肩周りには力布をつけます。
ここまでで、時間切れとなりました。次回上衿を付け衿先と絎けで完成します。
来年の夏は、すぐに着られますね(^_-)-☆
Hさんも、お忙しくてお久し振りです。
前回で浴衣が仕上がり、今日からは長襦袢です。
薄い鴇色から藤色に染め替えたという長襦袢、なかなか良い色に仕上がっています。
下がり藤(上がり藤)のたてわく柄が、背縫いで全然合っていないので、柄合わせをやり直しました。
ここが、縫い直しの面倒なところです。
片側の身頃だけ、今までの衿肩明きを前にずらして衿付けの中に隠します。
その為、背縫いを深くして、新しい衿肩明きを切ります。
これで、背縫いのたてわくがきれいに合いました。
長襦袢だって手抜きしないで柄を合わせましょう。綸子初体験のHさん、ツルツル、テレテレの布に四苦八苦でしたが身頃の標付け終了です。
午後からの参加で、捗りませんでしたが、次回からかんばりましょう。
揚げ縫いと背縫いが宿題です。
今日は、おふたり見学に来て下さいました。
ご入会希望されていたのですが、満席の為しばらくお待ち頂いていたのです。
10月から、開講日を増やす事にしたのでご入会されました。有難うございます。
皆様、お暑い中、お疲れ様でした。宿題頑張って下さいね。
にほんブログ村ランキング参加中です。
よろしかったらクリックを!
お訪ね下さいませ(^u^)