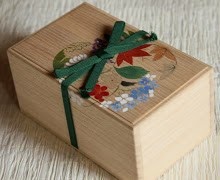着物には全く関係のない話題で申し訳ありません。
興味の有る方は、どうぞご覧下さい。
10数年前に、3年間くらい熱帯魚を飼っていました。
水草を植えて、水の中に揺れる緑を眺めて和んでいましたが、色々と忙しくなった事と、思い通りにいかない水草水槽の難しさに、挫折して止めておりました。
今年の夏、一寸したきっかけから、もう1度やってみようと思い立ち、再挑戦しています。
遠近感の無い写真になってしまいましたがご覧下さい。
45㎝の小型水槽ですが、水草でいっぱいです。
ピントが甘いですが、これは ↓ ドレープフィンバルブです。
背びれが開くと大きく広がり、黄色が目立って綺麗です。
この水槽に初めて入れた魚で8匹くらい居たのですが、次々死んで今日は3匹になり、今日は1匹弱っていました。
なぜかいつも、CO2(写真の白い粒々)が出る所でたむろしているんです。
それで酸欠になるのかと思って、CO2の装置を移動しました。もう手遅れかな...
上に居る茶色の丸いものは、石巻貝です。ガラスに付いた苔を食べてお掃除してくれます。
下の写真は、アンゴラバルブです。
魚の縞模様は、頭を上にして横縞か縦縞か見るのだそうです。
なので、これは横縞という事になります。
縞模様の魚は多いですが、横縞は少ないという事でした。
この魚は、小さいけれど存在感が有ると思って10匹買いました。
ところが、この魚小さすぎて、「ブッパ」(上の写真上部のステンレス円筒形)という水面の油膜を取り除く装置の中に、次々に入ってしまうのです。
見付けては救出していたのですが、それで弱ったり、朝見るとブッパの中で死んでいたりで、次々減って、今は2匹です。
下の写真で左上にいるのは、淡水の海老でヤマトヌマエビです。
水槽内の苔や魚の食べ残した餌を食べて水槽内のお掃除をします。
先日は、死んだ魚を食べているところを目撃。ギョッとしました。
死骸は見付けると取り除くのですが、草の間だったので気が付かなかったのです。
この赤みを帯びた魚↓は、ホワイトフィンロージーテトラです。
背びれ腹びれ尻びれの先が白くなっています。
この魚は丈夫で、5匹入れて今もすべて元気です。
魚が減って寂しくなってしまったので、これを増やしてこれだけにしようかな...と思っています。
下の写真中央、葉の上の水滴は、光合成の結果、葉からでた酸素です。
光合成が盛んになると、葉に無数の水滴が付きます。
水中に出た酸素なので、見た目は水滴ですが、厳密にいうと水滴では無いですよね。酸素粒かな...?(追記、気泡でした)
これらはお手入れグッズです。
上の二つは水草トリミング用の鋏です。
小さい方はスプリング 式の鋏ですが、左右どちらの手でも使えるので便利です。
両方とも刃先が曲がっていて使いやすくできています。切れ味も抜群です。
中央はピンセット、水草を植えたり、水槽内のゴミや死骸を取り除くのに使います。
次の三角は、水槽内の土を平らにならすものです。
下に付いている細い方は草や石の間の狭いところに使えて便利です。
一番下の5角形に棒のついた物は、二つのねじでカミソリのような刃を止めてあって、ガラスの表面に付いた苔を切り取るものです。
こういう道具を使って、まめにお手入れしないと、美しく維持できないのです。
右側の円筒形のステンレスは、外部フィルターです。
水槽内の水を取り込んで濾過して、また水槽に戻す役割をしています。
左の直方体は、クーラーです。
フィルターできれいになった水はこの中を通って25度に冷やされて水槽内に戻ります。夏の暑さがあまりに酷かったので、購入しました。
冬はこれを外し、水槽内のヒーターで水を温めて水温25度を保ちます。
これらは、水槽台の下に置いてあります。
上のグッズもフィルターも、水槽内の水を取り込んだり戻したりする部分のガラス製品や、油膜取のブッパやCO2添加の装置も、
ADAの製品です。
素材も形状も機能も、オーナーこだわりの製品なのです。
他のメーカーの物に比べると、かなりお高いのですが、やはりこちらに手が伸びます。
スカイツリーにある墨田水族館に、ADAオーナー、スタッフ力作の超大型水槽が有るのですが、いまだに見に行けていません。
近いうちに行きたいと思っています。
8月に、NHKTV番組「美の壺」で、これらの制作過程から紹介していました。
ADAでは、ネイチャーアクアリウムコンテストを毎年開催していて、今月28日に国際フォーラムで結果発表とパーティーが有るのですが、和裁塾開講日と重なってしまったので、残念ながら行けません。
コンテストの結果は、それぞれの参加者に順位の通知が届いていて、愛好家の方たちのブログで何方が何位と分かっているのですが、講義も有るというので行きたかったのです。
そんな訳で、忙しい身に、水槽管理というお仕事が増えて、益々忙しく暮らしています。
今日からお彼岸、お墓参りにおはぎ作り、更に忙しい1週間が始まりました。
手始めは、今朝の仏壇掃除です。
にほんブログ村ランキング参加中です。
よろしかったらクリックを!

お訪ね下さいませ(^u^)