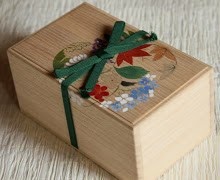Mさんは袷訪問着を縫っています。
今日は裏身頃を縫いました。
胴裏の脇縫いの標をして、つまみ縫いをしますが、私が間違えたので、やりなおしになってしまいました。ごめんなさい。
次に胴裏と八掛を縫い合わせ前幅の標をしました。衽付けまでが宿題です。
次回は表と裏の襟付けをします。
THさんは麻の長襦袢を縫っています。
背縫いまでできましたので、前の内揚げを縫い、後ろ幅と肩幅を標し、脇縫いに進みました。
身八つ下に忍び綴じを入れて、脇縫いは片返しで絎けました。
裾絎けまでが宿題です。次回は立襟付けに進みます。
Yさんはうそつき半襦袢です。
身頃が縫い上がって、両袖を縫いました。
マジックテープで取り外しができるようにしたいという事です。
次回にマジックテープの取り付けをして、馬乗りに閂止めをしたら完成です。
MYさんは竺仙の奥州小紋松煙染です。
脇縫いをして耳絎をしました。袖付け周りの縫い代をよく伸ばして、丁寧に絎けました。
次回は衽付けに進みますが、まだ標付けができていないので柄袷をして標付けからです。
Kさんは結城縮の単衣を縫っています。
お忙しくて宿題が進まないので、褄先の額縁を作ってから、脇の絎けをしました。
褄下と裾を絎ければ、襟付けです。残ったところは、できれば絎けてきて下さい。
Sさんは紬の単衣完成です。
前回完成目前だったのですが、問題発生で手直しとなったためちょっと延びてしまいました。
片袖付けと振り絎け、襟のスナップ付けで完成しました。
仕上げ前でしわが目立ちますが、ご覧ください。藤色の縞です。
和裁塾縁会で一番お若いSさん20歳代です。
お洋服はかわいいのがお好きなのに、この着物は地味ですね。
でもおしゃれなSさんは、自分流で可愛く着こなされるのでしょうね。
アップです。写真はグレーになってしまいましたが、ちょっと地味目な藤色です。
今日のお昼は桃六さんのおこわ弁当。季節限定の栗おこわです。
12時を過ぎると売切れてしまうので、早めに私がまとめて買いに行こうと思ったのです。
でも、みなさんが行って見たいという事で、私がお留守番をしていました。
思ったより栗が沢山入っていて美味しかった(^0_0^)
そしておやつは昨日の箱根旅のお土産「ちもと」さんの「湯もち」です。
今日の皆さんも、昨日のお二人もこのお菓子は初めてという事でした。
美味しいと喜んで頂きました。良かった(*^_^*)
紙箱にきれいに詰められて、美しく包まれています。今までにあちこちに差し上げましたが、どなたにも喜んで頂きました。
箱根の土産にお勧めです。
にほんブログ村ランキング参加中です。
よろしかったらクリックを!
お訪ね下さいませ(^u^)