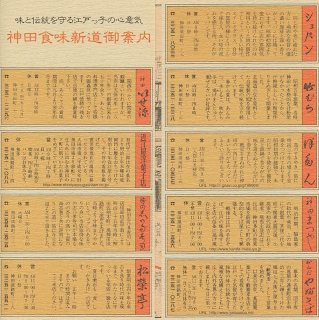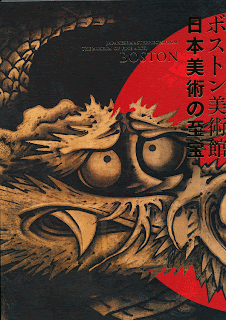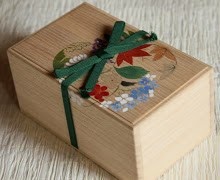何方もキャンセルされることなく、6名参加で賑やかに開講致しました。
Yさんは色無地の袖丈と裄出しが仕上がりました。
次は、うそつきの半襦袢を縫います。
新モスで、身頃と衿を裁ち、標を付けました。
背縫いを2度縫いして、脇縫いまで進みました。
次回は脇の絎けと裾絎け、衿付けまで進みたいです。
袖も縫いましょうね。
Mさんは浴衣を縫っています。
衽が縫い上がって褄下を絎け、いよいよ衿付けです。
共衿を地衿に縫いつけて、衿肩明きに力布を付け、衿を縫いました。
途中で針が折れる程堅くて大変でしたが、なんとか終了。
次回は衿を仕上げて、袖付けに進みます。お疲れ様でした。
Aさんも浴衣を縫っています。
脇縫いをなさっていらしたので、脇縫い代のミミ絎をしました。
袖付け周りの縫い代の伸ばしは、皆さん理解し難いところなのですが、片方を私が説明しながらやりますと、片側はご自分でできました。
なかなか感の良い方です。
衽の標付けが済んでいなかったので、標を付けて、前幅の標も付けました。
衽付けが宿題です。後3回で完成を目指します。
THさんは、前回体験で簡単肌襦袢を縫いました。
今日から小千谷縮の仕立てに入りました。
寸法の割り出し、布の見積もり、裁ち合せの確認をして鋏を入れます。
細かい格子なので、柄合わせが無くて楽でした。
標付けも順調に済んで、内揚げ縫いに進みました。
内揚げと背縫いが宿題です。
和裁は初めてでも、洋裁がお出来になるので、感が良いです。
針目もきれいにお縫いになるので、仕上がりもきれいだと思います。
頑張りましょうね。
TMさんは、単衣紬です。
衿付けまで出来て、次は掛け衿です。
掛け衿の絎けは細かく縫うので、時間が掛ります。
途中からは宿題にして、袖付けに進みました。
袖を付けて振りを絎けるのが宿題です。
途中で八寸名古屋の仕立てをしました。
お太鼓を決めたら、後はひたすらかがるだけです。
根気良く頑張って下さい。
着物の方は、衿先と衿裏の絎けで完成します。宿題頑張って下さいね。
Sさんも紬の単衣です。
居敷き当てを付けて、脇に忍び綴じを入れ、脇縫い代を居敷き当てと一緒に絎けました。
衽の標付けがまだだったので、標を付けました。
身頃の前幅標まで進めなかったので、次回にやります。
脇絎けの残りと、褄下の絎けが宿題です。
頑張って下さいね。
今日も皆さん熱心に針仕事に励みました。お疲れ様でした。
にほんブログ村ランキング参加中です。
よろしかったらクリックを!
お訪ね下さいませ(^u^)