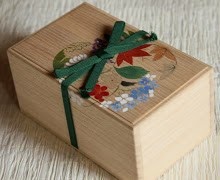今日からご入会のお二人が、帰り際に『とても楽しかった』とおっしゃいました。
嬉しいひとことです。
お二人は帽子のデザイン製作のお仕事をされているとの事、糸も針も扱いなれているので、順調なスタートでした。
Sさんは、浴衣のお仕立てです。
柄合せの難しい柄で、身頃を縫ってから袖や衽の柄を合わせるとという手順で進めることになりました。
Mさんは、単衣着物の袖丈と裄の直しです。
日頃から針仕事に慣れていらっしゃるので、きれいな針目でお縫いになります。
次回には、袖付け振り絎けで出来上がりそうです。
Nさんは、肌襦袢の続きです。
衿の絎けで苦戦しましたが、次回に袖付けで出来上がるでしょう。
小さな肌襦袢ですが、手縫いで仕立てるとなるとかなりの手間が掛ります。
でも、これで和裁の縫い方の基本は押さえられるので、浴衣に入ってもスムーズに進むでしょう。
あと少し頑張ってください。
Sさんは長襦袢の続きです。
前回から1週間しかなかったのにしっかり宿題をこなして、今日は竪襟付けと絎けができました。
次回は上襟を付けて、袖を付ければ出来上がりです。
Iさんは四つ身浴衣が仕上がりました。
腰揚げを仕上げて、付け紐を付けて可愛いくできましたね。
そして、ご主人の浴衣の続き、夏に間に合わせるべく大急ぎです。
今日は、お袖を縫って、身頃の標付けをしました。
完成目指して頑張りましょう。
お訪ね↓下さいませ(^u^)
〔 和裁塾 縁 会 〕
にほんブログ村ランキング参加中です。
よろしかったらクリックを!