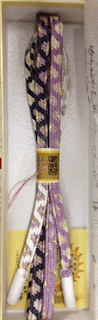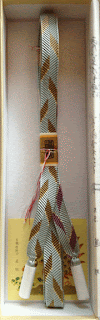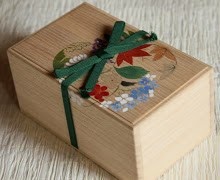今日は5人のご参加で、人形町で開講いたしました。
Ⅰさんは、木綿の単衣を縫っています。
襟をつけ終えて、きせをかけ襟幅を標ました。
襟先20㎝を残して襟幅をくけて、襟先を作りました。
襟の残りをくけて、襟付け完成です。
袖幅の標を付けたところで、時間には少し早かったのですが、区切良く終わりにしました。
次回は袖付で完成です。
Tさんは、検定試験の課題である部分縫いをしました。
三ツ身被布の襟付けは、色々なやり方があるのですが、和裁士会の技術書の中に説明が有ったのでその方法をお教えしました。
今までに何回か縫っていますが、今回は立襟の上端の止めも理解出来たようですし、小襟の返りもきれいに出来ました。
名古屋帯の手先も縫って見ました。
あとは練習して時間内に仕上げるように頑張って下さい。
SGさんは、小千谷縮です。
襟付けの続きから縫いました。
縫い上がってきせを掛け、身頃やおくみの縫込みを十分伸ばします。
襟幅の標をつけて、えり先20㎝を縫い残して襟裏をくけました。
襟先を作って残りをくけて、終了です。
お袖は、お家で付けていらしたので、もうこれで完成です。
お疲れ様でした。
波(?)に笹の絣柄の小千谷縮みです。
柄合せ、頑張りました。ご覧下さい(*^^)v
柄合せ、頑張りました。ご覧下さい(*^^)v
SZさんは、袷です。
今日はお袖を縫いました。
前回袖口布を回し付けして、袖口まで縫ってありましたので、口下の縫からです。
家庭和裁では、袖口下は四ツ縫いで仕上げることが多いのですが、今回は表と裏を別々に縫う方法で縫いました。
手間は掛かりますが、その分きれいに仕上がります。
口下を裏表別縫いにしてから、袖下まで四つ縫いに縫って丸みを作り、表に返して仕付けをします。
袖口には忍びを入れて、口ふきが不揃いにならないようにします。
袖口には忍びを入れて、口ふきが不揃いにならないようにします。
そして、振りは裏が5厘の控えになるように、裏表1分の差を付けて縫い合わせます。
ここで時間となってしまいましたが、片袖はほぼ完成です。
SZさんは、和裁経験がおありで、袷を何枚か縫った事はあるそうですが、この袖の縫い方には感動したとしきりにおっしゃっていました。
確かにきれいに縫えました。
確かにきれいに縫えました。
Kさんは、今日から2枚目の浴衣です。
裁ち切り身丈や総用尺を計算して、柄合せに進みましたが、反物の丈を測り間違えたか、総用尺を計算し間違えたか、最初の見積もり通りにいかず、時間が掛ってしまいました。
計算では内揚げを1寸程度撮れるはずでしたが、ほんの少しの内揚げになってしまいました。
柄合せもぎりぎりの丈で工夫して決めました。
身頃と衽の標付けまで何とか進みました。
次回は9月になってしまいますが、標付けを終えて袖縫いに入りたいと思います。
みなさんお暑い中お疲れ様でした。
次回は9月になる方もいらっしゃいますが、どうぞお元気で!
よろしかったらクリックを!
お訪ね下さいませ(^u^)